疲労感
疲労感とは
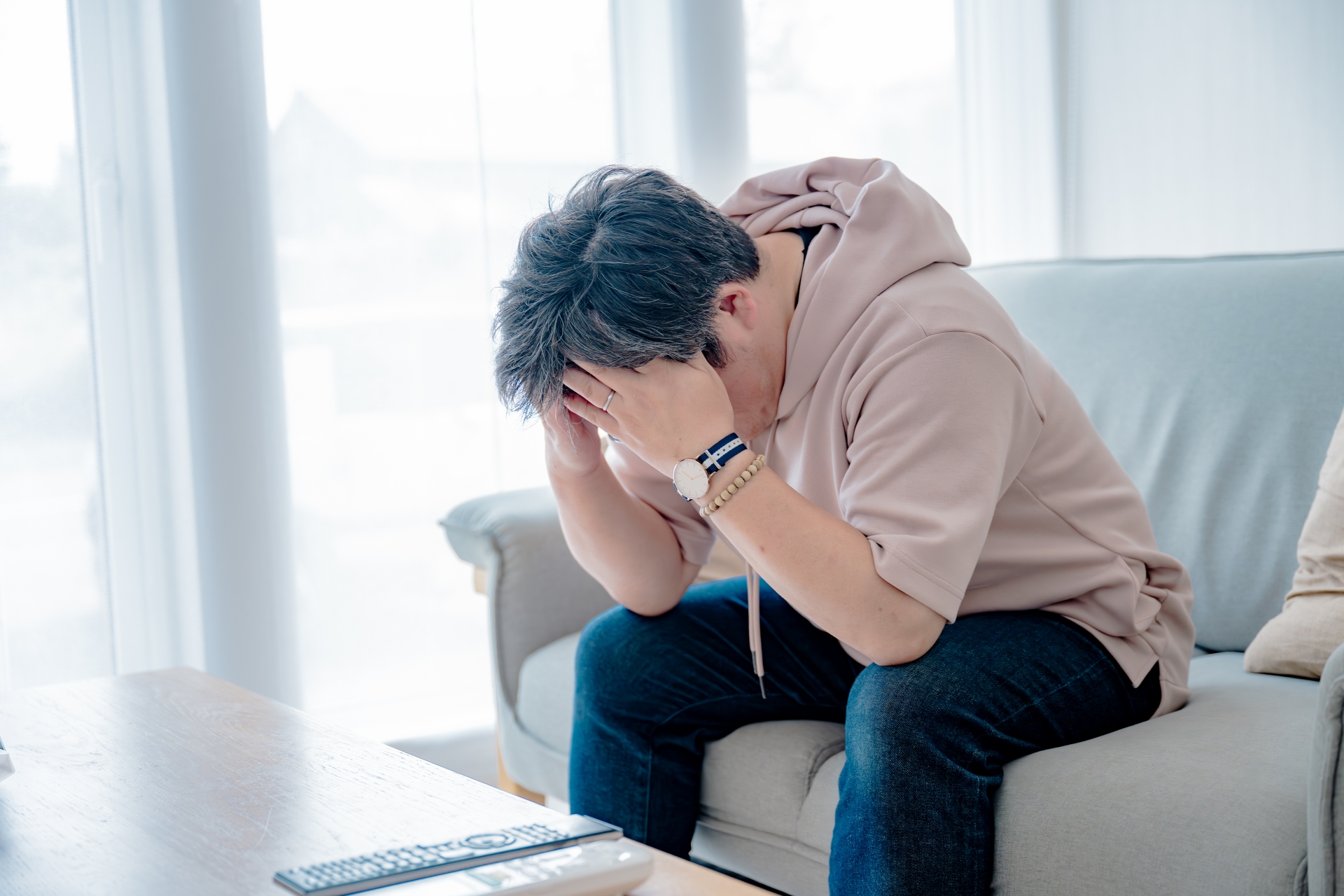
疲労感とは、体や精神が「疲れた」「しんどい」「だるい」と感じている状態を指します。疲労感と似た言葉に「倦怠感」があります。どちらも医学的に明確な違いは定められていませんが、疲労感は一時的な疲れやだるさの状態を指し、倦怠感は疲労感が長期的に続く状態や、強い疲れやだるさを感じる状態を指す場合が多いです。
日常生活を送るためには、心身が健康である必要があります。しかし、心や体が何らかの理由でエネルギー不足になると、疲労感として心身にサインが現れるのです。疲労感は休息を取れば改善する場合が多いですが、中には重大な病気が隠れている場合もあるため、違和感がある場合は医療機関の受診を検討しましょう。
疲労感の主な症状
疲労感の身体的な症状としては、主に体のだるさや重さがあげられます。さらに疲れが溜まると、頭痛や食欲不振などの症状が現れることもあるでしょう。 また、精神的な症状としては、集中力が続かずボーっとする、やる気が出ないなどがあげられます。悪化すると全てが面倒になったり、無気力になったりする症状が現れ、うつ病などの精神疾患を発症するきっかけになる可能性もあります。疲労感の原因
疲労感の原因には、大きく分けて「生理的なもの」「精神的なもの」「その他の病気によるもの」の3つがあげられます。生理的疲労
生理的疲労とは、過度な運動や活動によって生じる体の疲労を指します。 たとえば、長期間のランニングや激しい筋トレ、重労働などがあげられます。これらの運動や活動を行うと筋肉に疲労物質が溜まり、体のだるさやしんどさを感じるのです。 生理的疲労は、基本的に適切な休息を取れば回復が期待できます。しかし、単なる疲れだと思って体からのサインを無視し続けると慢性疲労につながる可能性があるため、十分な睡眠やマッサージ、健康的な食事などでしっかりとケアすることが重要です。精神的疲労
精神的疲労とは、心や脳に負荷を感じることで生じる精神的な疲労を指します。精神的疲労の例としては、仕事や勉強による長期間の集中や人間関係のストレス、感情的なできごとなどがあげられます。 これらの原因によって脳が過剰に働いたり、精神的なエネルギーが多く消費されたりすることによって、集中力や記憶力の低下、イライラする、不安になるなど思考や感情に影響が出ます。 精神的疲労を放置し続けると、うつ病や不安障害などの精神疾患を引き起こす可能性があるため、早めに対処することが大切です。器質性疾患
器質性疾患とは、臓器や組織に炎症や損傷が生じる病気のことを指します。代表的な例としては、肝硬変、慢性心不全、慢性腎不全、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などがあり、これらの疾患では症状の一つとして疲労感が現れることがあります。 疲労感の原因として器質性疾患が疑われる場合は、疾患の種類や進行度に応じた適切な治療が必要です。疲労感の治療
自律神経を整える
自律神経が乱れると疲労感が強くなりやすいため、意識的に整えることが大切です。自律神経を整える方法には、次のようなものがあります。 睡眠のリズムを整える 朝日を浴びる 適度な運動を取り入れる バランスの良い食事を心がける カフェインの摂取を控える ヨガやマインドフルネスなどのリラクゼーション法を取り入れる 生活習慣を見直し、自律神経のバランスを整えることで疲労感の軽減が期待できるでしょう。病院を受診する
生活習慣を見直しても疲労感が改善しない、または悪化する場合は、医療機関の受診をおすすめします。以下のような症状がある場合は、医療機関の受診を検討しましょう。- 疲労感が半年以上続いている
- 日常生活に支障が出るほどの疲労感がある
- 体重の急激な変化がある
- 発熱がある
- 皮膚や目の色に違和感がある

この記事の監修
メディカルクリニックパレ水天宮前 代表
石井 浩統
略歴
2005年3月 福井大学卒業
2005年4月 福井県済生会病院 臨床研修医
2007年4月 福井県済生会病院 外科医員
2010年1月 福井県済生会病院 外科医長
2011年4月 日本医科大学付属病院高度救命救急センター 助教・医員
2024年4月 メディカルクリニックパレ水天宮前開院